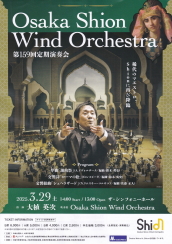
ザ・シンフォニーホール
大植英次指揮/Osaka Shion Wind Orchestra
ドヴォルザーク(鈴木英史編)/序曲「謝肉祭」
レスピーギ(鈴木英史編)/交響詩「ローマの松」
リムスキー=コルサコフ(佐藤正人編)/交響組曲「シェヘラザード」
座席:S席 2階CC列21番
Osaka Shion Wind Orchestra第159回定期演奏会
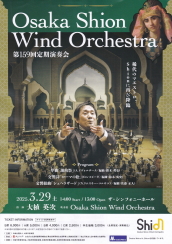 |
2025年3月29日(土)14:00開演 ザ・シンフォニーホール 大植英次指揮/Osaka Shion Wind Orchestra ドヴォルザーク(鈴木英史編)/序曲「謝肉祭」 座席:S席 2階CC列21番 |
Osaka Shion Wind Orchestraの定期演奏会にひさびさに行きました。客演指揮は、大植英次。大阪フィルハーモニー交響楽団桂冠指揮者、ハノーファー北ドイツ放送フィルハーモニー名誉指揮者、ハノーファー音楽大学終身正教授を務めています。
大植がShionを指揮するのは、祝100周年! オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ特別演奏会「カルミナ・ブラーナ」以来で、本公演が2回目です。本公演は「吹奏楽によるクラシック名曲」と銘打って、クラシック音楽の吹奏楽編曲が3曲演奏されました。
プログラムと一緒に配られた「シオンタイムズNo.75」には、今年1月26日に84歳で急逝した秋山和慶の特集記事が掲載されています。秋山は今年1月1日に自宅で転倒して入院。1月23日に指揮者活動の引退を発表しましたが、1月26日に訃報が流れたときは本当なのかと目を疑ってしまいました。秋山は大阪市音楽団時代の2001年に初共演、2003年度から特別指揮者・芸術顧問、2014年度から芸術顧問に就任し、定期演奏会には17回も出演しました。出演予定だった今年1月25日の第158回定期演奏会は、飯森範親が代役で指揮しました。2025年4月から秋山は名誉芸術顧問に就任することになりました。なお、首席客演指揮者には、ダグラス・ボストックが就任します。
お客さんは7割程度。制服の高校生が多くいましたが、学生価格は全席3000円と格安です。オーボエのGでチューニング。大植は譜面台なしで指揮しました。指揮台はいつもの踏み台があるものを持ち込んだのではなく、ホールのもののようです。
プログラム1曲目は、ドヴォルザーク作曲(鈴木英史編)/序曲「謝肉祭」。中低音を豊かに響かせて、ドイツ音楽のように勇ましい。木管楽器があまり聴こえないので、もう少し頑張ってほしいです。マリンバが活躍しますが、京都コンサートホール・ロビーコンサートVol.18「沓野勢津子 マリンバ・コンサート」で演奏した沓野勢津子でした。大植は67歳ですが、指揮姿が若い。中間部はメロディーラインをなぞるような指揮で、大きなサンドアートを描いているようにも見えました。
プログラム2曲目は、レスピーギ作曲(鈴木英史編)/交響詩「ローマの松」。大植が指揮する「ローマの松」は、オーケストラ版を大阪音楽大学第65回定期演奏会で聴きました。打楽器はティンパニを含めて7人+ピアノ+チェレスタ+ハープ+パイプオルガンの編成。「Ⅰ.ボルケーゼ荘の松」の冒頭はやや遅めのテンポで、色彩感がすごい。中低音が存在感を示して、立体的に聴こえて、オーケストラに負けない表現力です。練習番号8(Vivace)からテンポアップ。
間を空けて、「Ⅱ.カタコンブ付近の松」へ。トランペットソロは、下手の舞台裏から演奏。大植も下手袖のほうを見ながら指揮。Ancora piu mossoからの十六分音符のメロディーは、もともとテヌートがついていますが、よりテヌートで演奏。パイプオルガンも加わりますが、もう少し聴かせてもよいでしょう。練習番号12の2小節のfffでホルン×5がベルアップ。
「Ⅲ.ジャニコロの松」は柔らかい音色を作り出しました。練習番号14の3小節からのヴァイオリンソロはフルートが演奏。Grammofonoの鳥のさえずりは、スピーカーから流しました。
「Ⅳ.アッピア街道の松」は速めのテンポ。オーケストラでは第2ヴァイオリンが担っている付点四分音符+十六分音符の音型を、ミュート付きのトランペット×2が演奏するのが意外なアレンジです。練習番号20の5小節からのバンダは、2階席左後方でFlicorni Sopraniをコルネット×2が演奏(譜面台付き)。私の席に近いのでよく聴こえました。大植は後ろを振り向いて指揮しました。練習番号24からFlicorni Tenoriをフリューゲルホルン×2も追加。続いて、2階席右後方から、Flicorni Bassiをバス・トロンボーン×2が演奏(プログラムにはバス・トランペットと記載されていましたが、誤記でしょうか)。素晴らしい演奏でしたが、バンダにはライトが当たっていないので、少しかわいそう。大植は身を屈めて両腕を振るような指揮。カーテンコールでは舞台裏で演奏していたトランペット奏者もステージへ呼ばれました。
休憩後のプログラム3曲目は、リムスキー=コルサコフ作曲(佐藤正人編)/交響組曲「シェヘラザード」。佐藤正人は、尚美学園大学客員教授、武蔵野音楽大学非常勤講師、秋田吹奏楽団音楽監督、川越奏和奏友会吹奏楽団音楽監督兼常任指揮者、ソノーレ・ウィンドアンサンブル音楽監督、立正大学吹奏楽部音楽監督などを務めています。楽譜は未出版(ロケットミュージックから出版予定)とのことで、演奏例が少ないようです。よくできたアレンジで、オーケストラを吹奏楽のどの楽器に置き換えたかではなく、ウインドオーケストラの総合的で聴かせる編曲です。オーケストラではどの楽器が演奏していたかを考える余地を与えず、無理して吹奏楽の楽器が演奏している印象はありません。
「Ⅰ.海とシンドバッドの船」はやや速めのテンポ。オーケストラでのヴァイオリン独奏は、フルート→クラリネット→ピッコロの順に、各楽器にメロディーが受け渡されるのが特徴です。その次のヴァイオリン独奏もアルトサックス→クラリネットに受け継いで演奏されます。
続けて「Ⅱ.カランダール王子の物語」へ。ファゴットソロ、オーボエソロと続いて、トゥッティで演奏される71小節からは、オーケストラの原曲にはない鉄琴(グロッケンシュピール)が入って華やか。132小節からのトランペット×3とトロンボーン×3の掛け合いが聴きごたえあり。401小節からのトゥッティのメロディーは厳かささえ感じました。
「Ⅲ.若き王子と王女」の70小節からのクラリネットソロとそれに続くピッコロは弱奏で演奏して、音量を抑えるところは抑えます(オーケストラのスコアでもppp)。後半のアルトサックスがヴァイオリン独奏を担当。
「Ⅳ.バグダッドの祭、海、青銅の騎士のある岩にて難破、終曲」の8小節からのヴァイオリン独奏はアルトサックス×2で演奏。29小節からはソプラノサックス+アルトサックス×3で演奏。30小節(Vivo)からはやや速めのテンポ。金管楽器で演奏される105小節からは遅く堂々と演奏して、テンポを対比させましたが、ややアインザッツの乱れがあるのが残念。速いテンポのまま586小節に突っ込み、そのままテンポを落とさずに演奏。最後の弱奏はちょっと音程が不安定で繊細さに欠けました。こういうところが残念ながら京都市交響楽団とのレベルの違いを感じました。
カーテンコールでは、3月末で退団するトランペット奏者の村上広明に、特大の花束が贈呈されました。メンバーは涙。大植も握手。
人数はそれほど多くない(60名程度)のによく鳴って、技術力もあります。大植との相性はよさそうです。次は第161回定期演奏会(2025.6.28)のオール・ラヴェル・プログラムを聴きに行くので楽しみです。
大植もまた指揮してほしいです。なお、大植英次はスケジュールが合わないのか、第6回まで指揮していた尼崎市での「中学・高校吹奏楽部公開レッスンコンサート」を今年も指揮しません。残念です。
