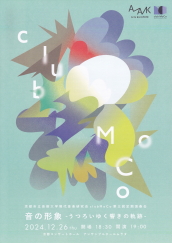

2024年12月26日(木)19:00開演
京都コンサートホールアンサンブルホールムラタ
森脇涼指揮/京都市立芸術大学現代音楽研究会clubMoCo
藤本紗朗(ピアノ)、石井悠紀子(ヴィオラ)
ファウスト・ロミテッリ/AMOK KOMA
トリスタン・ミュライユ/別離の鐘、微笑み~オリヴィエ・メシアンの追憶に
オリヴィエ・メシアン/異国の鳥たち
ジェラール・グリゼイ/「音響空間」よりⅠ.プロローグ、Ⅱ.ペリオド、Ⅲ.パルシェル
座席:自由
京都市立芸術大学現代音楽研究会clubMoCo第三回定期演奏会「音の形象-うつろいゆく響きの軌跡-」
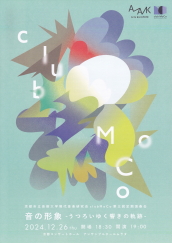  |
2024年12月26日(木)19:00開演 森脇涼指揮/京都市立芸術大学現代音楽研究会clubMoCo ファウスト・ロミテッリ/AMOK KOMA 座席:自由 |
開演前の18:45からプレトーク。予告なしかと思いましたが、Instagramで告知されていました。clubMoCo部長の中野宏紀(作曲専攻4回生)と顧問の酒井健治(作曲専攻准教授)が登場。中野は「グリゼイは酒井の授業で分析した」。酒井は「グリゼイはパリで研究した。正しいピッチがとても難しい。最後のオチがすべらなかったらいい」と語りました。非常勤講師の有馬純寿が協力してくれたと紹介しました。
プログラム1曲目は、ファウスト・ロミテッリ作曲/AMOK KOMA。2001年の作品。ロミテッリはイタリアの作曲家で、スペクトル楽派の第2世代の作曲家と評されます。「AMOK KOMA(アモク コマ)」はラテン語の回文で、不安定な精神状態が描写した作品とのこと。11名で演奏。前列は左から、フルート(ピッコロ持ち替え)、クラリネット、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、バスクラリネット(クラリネット持ち替え)の順。後列は左からピアノ、打楽器、キーボード、エレクトロニクス(=パソコン)2名。指揮の森脇涼は、2024年に指揮専攻を卒業して、神戸市混声合唱団の副指揮者などを務めています。演奏前に各楽器をマイクコードにつなげる作業があり、スピーカーがステージ前方に5台、2階席の左右に各1台、客席後方に3台設置されていました。
ピアノと鉄琴(ヴィブラフォン)の金属的な音響が強く、管楽器の存在は薄い。一応テンポやリズムはある作品です。途中から、スピーカーから演奏していない音を流します。つまり、録音した音をスピーカーから流しましたが、演奏後の部長と副部長のトークでは、集音するためにステージにマイクを13本立てていたとのこと。客席後方にもスピーカーがあったことに気がつかず、音がホール内を巡回する効果はあまり得られなかったように感じるので、スピーカーの音量をもう少し上げたほうがよかったでしょう。ステージ上のパソコンを操作して、ややノイズまじりの音になったりしました。どんな楽譜か見てみたいです。最後は木管奏者が口笛を吹いているかと思ったら、ワインボトルを吹いていたようです。舞台転換中にステージのスピーカーは撤去されました。
プログラム2曲目は、トリスタン・ミュライユ作曲/別離の鐘、微笑み~オリヴィエ・メシアンの追憶に。1992年の作品で、ピアノ独奏による演奏です。奏者は女性でしたが、パンフレットに名前はありませんでした。ミュライユの作品は京都市交響楽団第658回定期演奏会で「シヤージュ(航跡)」を聴きました。音域が広く、メシアンっぽい音づかいですが、特殊奏法はありません。最後は長い音が消えます。
プログラム3曲目は、オリヴィエ・メシアン作曲/異国の鳥たち。1955~56年の作品で、いずみシンフォニエッタ大阪第15回定期演奏会「管楽器とパーカッションの魅力」で聴きました。再び指揮台が設置されて、ピアノは下手に配置。ピアノ独奏の藤本紗朗(しゃろむ)はピアノ専攻の4回生で、clubMoCoの第2代部長を務めました。メンバーは色とりどりのシャツで登場。1列目はフルート、クラリネット、クラリネット。2列目はピッコロ、クラリネット、クラリネット、トランペット、ホルン×2。3列目はファゴット、バスクラリネット。後列の打楽器は全員で5人います。弦楽器はなく、管楽器と打楽器の編成です。
47種類の鳥の声が登場しますが、「鳥のカタログ」のようにピアノソロが多く、テンポは速く技術的に難しいですが、なんと暗譜で演奏していてびっくり。打鍵をはっきり聴かせました。打楽器の色彩感がいい。ゴング(3 Gongs)は聴こえないくらいソフトに叩きます。シロフォンがスティックを中央に集めるようなグリッサンドが効果的。森脇はリズミカルに指揮しました。最後のコーダは重々しい。
休憩後のプログラム4曲目は、ジェラール・グリゼイ作曲/「音響空間」よりⅠ.プロローグ、Ⅱ.ペリオド、Ⅲ.パルシェル。1974~85年の作品で、全曲は6曲からなり約1時間半かかりますが、本公演では前半の3曲が演奏されました。ちなみに、第1曲から、第4曲「モデュラシオン」、第5曲「トランジトワール」、第6曲「エピローグ」に進むにつれて、徐々に編成が大きくなるように作曲されています。全曲は休みなく演奏されます。1列目はヴァイオリン×2、ヴィオラ、空席、チェロ、コントラバス。2列目はフルート×2、オーボエ、クラリネット×2、バスクラリネット。3列目は、ホルン×2、トロンボーン。その後ろにキーボード、打楽器×2。
プログラムの曲目解説によると、緻密な音楽思想や理論によって作曲されているようですが、初めて聴いただけでは理解できません。また、「音響空間」という曲名の割には、意外にも舞台裏から演奏するなどの演奏効果はありません。
演奏前にホール内の照明が消えて真っ暗に。「Ⅰ.プロローグ」はヴィオラのみの演奏。石井悠紀子(修士課程1回生)が登場して、ステージの一番後ろで立って演奏。ヴィオラのみスポットライトが当たります。5つの音から成るモティーフを変奏して繰り返していきます。譜面台を4つ並べて演奏するほどかなり長いソロで、石井のX(@yuyuyu0241)によると18分もあるとのこと。音域や跳躍が広くなって、モティーフが発展し、グリッサンドのような奏法や、高音で激しいノイズ音を出します。ヴィオラでこんな音が出せるんですね。
ステージが明るくなり、石井が歩いて指揮者の正面の空席だった席に座って、そのまま「Ⅱ.ペリオド」へ。森脇が指揮棒なしで指揮して、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、フルート、クラリネット、トロンボーンの7名で演奏。トロンボーンがスタッカートで「ポ」という音を演奏。クラリネットとコントラバスの掛け合い、トロンボーンのミュート音、ヴァイオリンのノイズや不協和音が続きます。ヴァイオリンソロとヴィオラとの掛け合いで、音程が合わないので、ヴィオラ奏者が立ち上がって、ヴァイオリン奏者をのぞきこむ演技。指揮者は腕組み。ヴィオラがチューニングをして、ヴァイオリンとフルートとチェロとコントラバスとクラリネットによる変わった音響が聴けました。
トロンボーンソロが派手に鳴って、「Ⅲ.パルシェル」で、ついに18名全員による演奏。コントラバスが激しいボウイングで、同じモティーフを繰り返します。打楽器も参加して、キーボードでは何かの打楽器の音を演奏。バスクラリネットはコントラバスクラリネットを演奏。ヴァイオリン×2を中心に高音で演奏。ライオンローア(太鼓のような楽器から吊るした糸を引っ張って音を出す楽器)で獣の鳴き声みたいな音を聴かせました。ドラも強奏。下降音型を全員で演奏。大太鼓に砂の袋をなすりつけたり、ヴァイオリン奏者が弓をカサカサしたり、こそこそ私語をしたり、楽譜(森脇によると、トレーシングペーパーらしい)を引っ張ってガサガサ音を立てたりします。指揮者は汗をぬぐい、スコアを閉じて横のイスに座りました。最後に打楽器奏者が最後列でシンバルを両手に構えて、今にも鳴らすように見せたところで照明が消えて終わり。意外な終わり方で、客席からは笑いがこぼれました。プレトークで酒井が「最後のオチがすべらなかったらいい」と話していましたが、十分すぎるインパクトでした。視覚的にも楽しめて、フランス人らしいユーモアですが、これは音楽そのものが解体されて、何も音を発しなくなったことを表現しているようです。21:15に終演。
正課授業ではなく、課外活動で学生が自主的に取り組んでいる姿勢がまず評価されるべきです。演奏レベルはとても高く、期待以上でした。スペクトル楽派の作品に興味が持てたわけではなく、難しい作品でしたが、演奏がよくて楽しめました。森脇涼の指揮がとても落ち着いていて、すばらしい。丁寧に奏者にキュー出しして、安心して演奏できる指揮です。次回の演奏会にも期待します。
