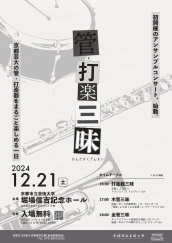管・打楽三昧
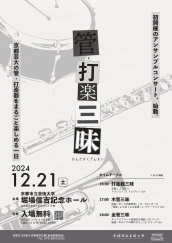 |
|
2024年12月21日(土)
京都市立芸術大学堀場信吉記念ホール
京都市立芸術大学音楽学部・大学院 管・打楽専攻生
15:30開演 打楽器三昧
トーマス・ゴーガー/5人の打楽器奏者のための「ゲインズボロー」第3楽章
イヴァン・トレヴィーノ/トランスⅠ
ジョン・ササス/京都
アンディ・ハンスバーガー/ダーク・パッセンジャー
アンディ・アキホ/ピラーⅦ
17:00開演 木管三昧
ジャック・イベール/3つの小品
アラン・スティーヴンソン/2つのオーボエとイングリッシュホルンのためのミニトリオ 第1楽章、第4楽章
エクトル・ベルリオーズ(山田忠臣編)/序曲「ローマの謝肉祭」
多久潤一郎/ローズ・ローザ
フランツ・ダンツィ/木管五重奏曲第2番第1楽章
ポール・タファネル/木管五重奏曲第1楽章
レオシュ・ヤナーチェク/木管六重奏のための組曲「青春」第1楽章、第2楽章、第4楽章
19:00開演 金管三昧
ウィリアム・バード(エルガー・ハワース編)/オックスフォード伯爵の行進曲
マシュー・ロック/国王陛下のサックバットとコルネットのための音楽
和田信/週末のポップ組曲
宮川彬良/金管五重奏のための小品集「子宝」
酒井格/国境の島
レオナルド・サルセード/ディベルティメント
エドヴァルド・グリーグ(野間裕史編)/組曲「ホルベアの時代から」
座席:自由
|
京都市立芸術大学の管・打楽専攻生による演奏会「管・打楽三昧」に行きました。京都市立芸術大学は昨年10月に崇仁キャンパスに移転しましたが、この「管・打楽三昧」は今年度から始まったアンサンブルコンサートです。「打楽器三昧」「木管三昧」「金管三昧」の3部構成で、打楽器と管楽器のアンサンブルが一気に楽しめます。15:30開演で、20:30終演予定の長丁場です。入場無料ですが、前日までに予約フォームから申し込みが必要でした。
15:10に開場。受付で名前を伝えます。座席は全席自由でした。プログラムが配布されましたが、曲目だけで解説は掲載されていません。演奏曲目は、来年2~3月に開催する各楽器のアンサンブルコンサートでの演奏予定曲からのダイジェストといった様相です。プログラムに掲載された出演者一覧によると、フルート9名、オーボエ7名、クラリネット8名、バスーン2名(うち1名は賛助出演)、サクソフォン11名、トランペット9名、ホルン7名、トロンボーン9名、ユーフォニアム4名(うち1名は交換留学生)、チューバ2名、パーカッション8名の構成です。お客さんは少なく、50人くらいでした。
15:30開演 打楽器三昧
打楽器専攻生は全員で8人で、楽器も自分たちで移動しました。曲間に作品解説のMCを順番で担当しました。
プログラム1曲目は、打楽器五重奏で、トーマス・ゴーガー作曲/5人の打楽器奏者のための「ゲインズボロー」第3楽章。解説によると、1965年作曲で、古典的な作品とのこと。この曲はびわこミュージックハーベスト 打楽器&マリンバ 公開アカデミー&演奏会で聴いたので、懐かしく思い出しました。楽器の配置は違って、本公演ではヴィブラフォンとグロッケンシュピールを客席に背を向けて配置しました。ホールがすごく響くので、響きすぎて輪郭がぼやけがちです。
プログラム2曲目は、打楽器四重奏で、イヴァン・トレヴィーノ作曲/トランスⅠ。2020年の作曲で、紙の削減を推奨している団体(Green Vibes Project)からの委嘱作品のため、楽譜もタブレット端末とのこと。3つの楽章から成る作品の第1楽章のようです。演奏前のMCでは「スマートフォンの持続音が続き、視覚と聴覚の一体感でトランス状態になる」と解説しました。奏者が横一列で並び、ホール内が真っ暗になりました。4台の白い光のライトが点いて、空き缶を叩くような金属音がしますが、暗くて何をしているのか見えません。4台のライトが同時に点滅したり、激しくなったり、激しい点滅がまさにトランス状態で、刺激的な作品です。演奏後に照明が明るくなると、金属のボウルをスティックで叩いていたことが分かりました。まさに新時代の打楽器アンサンブルです。
プログラム3曲目は、打楽器五重奏で、ジョン・ササス作曲/京都。ササスはニュージーランドの作曲家で、この作品は2011年に台湾で初演されました。京都で聴いたジャズピアノの印象をもとに作曲されて、ヴィブラフォン×2、マリンバ×2、ドラムスの編成で、和楽器はありません。この作品に京都らしさを期待すると肩透かしを食らうでしょう。速いテンポで流れるような作品で、息のあったアンサンブルです。弦の弓でマリンバの鍵盤をこする奏法がありました。最後は禅の世界観でしょうか、静かに終わります。
プログラム4曲目は、打楽器三重奏で、アンディ・ハンスバーガー作曲/ダーク・パッセンジャー。2015年の作品で、3セットのボンゴ(6台)を3人が取り囲むように叩いて、立ち位置を移動します。暗譜で演奏。これだけスムーズに演奏するにはかなりの練習が必要です。wire brushをボンゴになすりつけるように叩くことで、砂のような音に聴こえました。ボンゴの上に5 cup gongsを置いて、中間部は仏教のような静寂の世界です。後半は速いテンポで、ボンゴの横にスタンドシンバル(スコアでは3 opera gongs)を置いて、音色が加わりました。
プログラム5曲目は、打楽器四重奏で、アンディ・アキホ作曲/ピラーⅦ。アキホは日系アメリカ人。この作品は組曲「セブン ピラーズ」の最終楽章で、ラスト3分は5000以上の音が演奏されるとのこと。一番後ろの奏者(Percussion 4th)が金属音がする変な楽器(crotales)を演奏しました。また、木製の鍵盤楽器と鐘と、足でドラム(Kick Drum)も一人で担当して、ノリノリで演奏しました。私の席からはよく見えなくて残念。4人で演奏しているとは思えない作品でした。
最後に8人全員が登場して、講師の森本瑞生があいさつ。毎週水曜日の「管打合奏」の授業で取り組んでいるアンサンブルの成果発表会として企画したと説明しました。16:30に終演。選曲が多彩で、打楽器のおもしろさを堪能できました。本日演奏した曲を3月に開催する「THE PERCUSSION VOL.15」でも演奏するとのことですが、もうここまで仕上がっているとはびっくりしました。

17:00開演 木管三昧
続いて木管楽器によるアンサンブル。舞台裏でチューニングしてから登場。曲間にMCはなく、淡々と進行しました。
プログラム1曲目は、木管五重奏で、ジャック・イベール作曲/3つの小品。左から、フルート、オーボエ、ホルン、バスーン、クラリネットの順。ホールがすごく響くので、アーティキュレーションをはっきりつける必要があります。ブレスも目立ちました。ホルンがミュートを使うのが珍しい。
プログラム2曲目は、オーボエ三重奏で、アラン・スティーヴンソン作曲/2つのオーボエとイングリッシュホルンのためのミニトリオ 第1楽章、第4楽章。左から、オーボエ、イングリッシュホルン、オーボエの順。今年度から加瀬孝宏(元東京フィルハーモニー交響楽団首席オーボエ奏者)が准教授に着任しました。のびやかな演奏。
プログラム3曲目は、サクソフォン八重奏で、エクトル・ベルリオーズ作曲(山田忠臣編)/序曲「ローマの謝肉祭」。左から、ソプラノ×2、アルト×2、バリトン×2、テナー×2の順。ごちゃごちゃして聴こえるので、表情の付け方など改良の余地ありです。
10分休憩後のプログラム4曲目は、フルート四重奏で、多久潤一朗作曲/ローズ・ローザ。立っての演奏で、フルート×3と一番右はアルトフルート。アイコンタクトをとりながらの演奏でアンサンブルにふさわしい。2楽章と3楽章で尺八のような息遣いでかすれた音を出しました。
プログラム5曲目は、木管五重奏で、フランツ・ダンツィ作曲/木管五重奏曲第2番第1楽章。左から、フルート、オーボエ、ホルン、ファゴット、クラリネットの順。音色に統一感があって聴きやすい演奏。他の楽章も聴きたいです。
プログラム6曲目は、木管五重奏で、ポール・タファネル作曲/木管五重奏曲第1楽章。左から、フルート、オーボエ、ホルン、ファゴット、クラリネットの順。アーティキュレーションがはっきりしていてよく揃っています。表情も豊か。
プログラム7曲目は、木管六重奏で、レオシュ・ヤナーチェク作曲/木管六重奏のための組曲「青春」第1楽章、第2楽章、第4楽章。左から、フルート、オーボエ、ファゴット、ホルン、バスクラリネット、クラリネットの順。バスクラリネットが入るだけで、雰囲気がずいぶん変わります。ホルンに見せ場が多い。安定感があるアンサンブルでした。
演奏終了後に、加瀬孝宏と福田彩乃(非常勤講師、サクソフォン)があいさつ。インフルエンザで出場できなくなった団体があったと明かしました。18:30に終演。
19:00開演 金管三昧
最後は金管楽器によるアンサンブル。舞台裏でB♭でチューニング。曲間に作品解説のMCがありました。
プログラム1曲目は、金管・打楽器11重奏で、ウィリアム・バード作曲(エルガー・ハワース編)/オックスフォード伯爵の行進曲。左から、トランペット×4、ホルン、パーカッション、チューバ、トロンボーン×4の順。ルネサンス時代の作品で、ドラムソロから始まります。響きすぎてぼやけがちですが、勇壮で輝かしい行進曲。
プログラム2曲目は、金管五重奏で、マシュー・ロック作曲/国王陛下のサックバットとコルネットのための音楽。バロック時代の作品で、サックバットとはトロンボーンの前身の楽器とのこと。左から、コルネット×2、ホルン、ユーフォニアム、チューバの順。短い6曲からなります。コルネットが輝かしい。残りの3人は伴奏に徹します。
プログラム3曲目は、ユーフォニアム・チューバ・ドラムス五重奏で、和田信作曲/週末のポップ組曲。1曲目「フライデーナイト」、2曲目「サタデー」、3曲目「サンデー」の3曲からなります。全員が客席に向かって正面を向く変わった配置で、1列目がユーフォニアム×2、2列目がチューバ×2、その後ろがドラムス。1曲目「フライデーナイト」はチューバの7拍子のメロディーがウキウキ気分で、3曲の中で金曜日の夜が一番楽しそう。2曲目「サタデー」はショッピングセンターのBGMのよう。3曲目「サンデー」は最後に「きよしこの夜」がチューバソロで引用されます。
プログラム4曲目は、金管五重奏で、宮川彬良作曲/金管五重奏のための小品集「子宝」。左から、トランペット、ホルン、チューバ、トロンボーン、トランペットの順。演奏前のMCで、第3楽章「生態系のマーチ」で、客席にも演奏への参加の呼びかけがありました。足と手を交互に鳴らす動作で、奏者を見本にして練習。突然始まって突然終わるので、第1トランペット奏者がストップの合図をするとのこと、演奏は、第1楽章「不良の天才」はよくまとまっています。第2楽章「ゼリー状の幸福」とは鼻水のこと。ミュート付きのトランペットがメロディーを担当。第3楽章「生態系のマーチ」はチューバソロから始まって、メロディーが軽やか。MCで説明があった手拍子と足踏みは、本当に突然始まって突然終わりました。
10分休憩後のプログラム5曲目は、金管十重奏で、酒井格作曲/国境の島。左から、トランペット×2、ホルン、ユーフォニアム、チューバ、ホルン、トロンボーン×2、トランペット×2。冒頭のトランペットソロが、マーラー「交響曲第5番」第1楽章冒頭のトランペットソロからはじまってびっくり。最後にも現れます。人数が多い割には、演奏はよくまとまっていて整っています。なお、国境の島は特定の国を描いたわけではないようです。
プログラム6曲目は、金管六重奏で、レオナルド・サルセード作曲/ディベルティメント。トランペットとトロンボーンだけのアンサンブル曲は珍しいとのこと。左側のトランペット×3と右側のトロンボーン×2+バストロンボーンの掛け合いが楽しい。3曲目の「間奏曲」は全員がミュートをつけてコラールを演奏しました。
プログラム7曲目は、金管十重奏で、エドヴァルド・グリーグ作曲(野間裕史編)/組曲「ホルベアの時代から」。この曲のみGでチューニング。左から、トランペット×4、ホルン、トロンボーン×4、チューバ。冒頭からすばらしいハーモニー。金管楽器だけで演奏するのに違和感のない編曲と演奏で、第1曲「前奏曲」は、トランペットが細かな音符を演奏しました。第4曲「アリア」はチューバソロ。第5曲「リゴドン」はトランペットが大健闘。力強く終わりました。
教授の村上哲があいさつ。「このコンサート開催の経緯を話そうと思ったが、長くなるので来年に話す」とのこと。「授業の延長で補講の位置付けなので、入場無料にしている」と説明して、「来年は2025年12月20日に開催する」と予告しました。早坂宏明(非常勤講師、トランペット)が今年度末で定年退職されると紹介。早坂を「京芸の金管のサウンドを作った名物先生」と紹介しました。最後にアンコール。早坂は「1972年の札幌オリンピックのマーチ」と説明して、山本直純作曲/白銀の栄光を指揮。金管全員と打楽器で演奏。輝かしい演奏でした。予定よりもオーバーして、21:00に終演しました。
昨年10月に新キャンパスに移転してから、今年11月には吹奏楽の新たな演奏会として「オータムウインズフェスト」が開催されて、各楽器によるアンサンブルと京都市立芸術大学シンフォニックウィンドアンサンブルの演奏が披露されましたが、それに加えて、管楽器と打楽器のアンサンブルの演奏を聴ける機会が増えるのはとてもうれしいです。来年も期待しています。