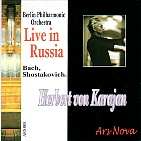
1969年5月29日 モスクワ音楽院大ホール
J.S.バッハ/ブランデンブルク協奏曲第1番
ショスタコーヴィチ/交響曲第10番
Ars Nova ARS008
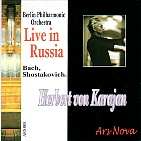 |
|
ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1969年5月29日 モスクワ音楽院大ホール J.S.バッハ/ブランデンブルク協奏曲第1番
|
ベルリンフィルと演奏旅行中の1969年のモスクワ公演ライヴ録音です。LP時代にメロディアからリリースされたようですが、廃盤となっていました。今回、国籍不明?の「アルスノヴァ」レーベルよりリリースされました。
カラヤンのライヴ録音は数が少ないので、それ自体とても貴重な記録ですが、この録音はその中でも格別の意味を持つ録音であると言えるでしょう。と言うのも、ショスタコーヴィチの交響曲第10番を客席で聴いていたショスタコーヴィチ本人が、演奏後感激のあまりステージに上がったというエピソード付きの演奏会だからです。
カラヤンは作曲者が客席で聴いていることを事前に知っていたのでしょうか?ともかく、この録音により、カラヤンが作曲者の前でどんな演奏をしたのかを聴くことができます。
まずは、そのショスタコーヴィチから。
結論を先に言うと、非の打ちどころのないすばらしい演奏であると思います。
第1楽章の冒頭から、丁寧で精巧な音楽作りがうかがえます。スタジオ録音と変わらない冷静な姿勢でカラヤンはタクトを振っていると言えます。
練習番号9(4'00")では、弦楽器のうねりにゾクッとさせられました。カラヤンならではの演出が聴けます。
練習番号41(12'26")からのクライマックスでは、打楽器を思い切り叩かせています。また、金管強奏の威力もすさまじい限りです。
このライヴでは、強奏はスタジオ録音よりも吹っ切れたように演奏しています。
第2楽章は、四分音符=176というアレグロですが、まさに爆走、約4分で駆け抜けています。終始緊張度の高い音楽が続きますが、この楽章の音楽を理想的に再現していると言えます。ベルリンフィルにしてなせる演奏です。八分音符の鋭い刻みが兵隊の進軍に聞こえてくるのは私だけではないでしょう。ヴォルコフの『ショスタコーヴィチの証言』では、この楽章は「スターリンの肖像」を描いた音楽であると言われていますが、その記述にも納得させられる演奏です。
第3楽章は、前半部はソロが室内楽的に断続的に続きますが、まさに一糸乱れぬアンサンブルを披露しています。どれをとってもすばらしい演奏です。
練習番号127(7'42")から、弦楽器で「D−S−C−H」のテーマが出たその後ろでトランペットが四分音符と八分音符の音型を演奏しますが、カラヤンはこのトランペットを強奏させています。トランペットの活躍は、カラヤンの代名詞とも言えるだけあって、ここでも大切に扱われています。
第4楽章は、中盤から再び四分音符=176のテンポで疾走しますが、音程の乱れもなく、集中力が最後まで持続しています。ライヴとは思えない完成度の高い演奏です。
全曲を通して、聴かれる音楽は明らかにショスタコーヴィチの作品ですが、同時にカラヤンの「作品」でもあります。この演奏が正当な解釈であると言い切らんばかりのカラヤンの自信と説得力を感じますし、どっしりと根を張ったベルリンフィルの演奏も見事です。カラヤンの美意識とショスタコーヴィチの作品がうまく融合した演奏であると言えるでしょう。
周知のように、カラヤンはショスタコーヴィチの作品は一生涯でもこの交響曲第10番しか演奏しませんでした。交響曲第10番は、スタジオ録音でも2種(1966年,1981年)残しています。未聴ですが、この3種の録音の聴きくらべは興味があります。
演奏会の前半に置かれたバッハは、スタジオ録音よりもいきいきとした開放的な演奏です。特にオーボエが表情豊かです。チェンバロを弾いているのは、カラヤンでしょうか? よく聞こえます。
気になる録音状態は、会場ノイズが少ないので鑑賞には全く問題ありません。ただし経年の劣化により、細部がいまひとつ鮮明でないのが残念です。この演奏会場は体積が大きいのでしょうか? 残響がかなり多めに録られています。それゆえ、強奏では地響きに似た感覚が楽しめます。DGの録音を聴き慣れた耳には衝撃的な録音ですが、この貴重な演奏会を後世に伝えるすばらしい記録であると言えるでしょう。
余談ですが、ジャケットに解説書がついていないなどやや質素な体裁なのが残念ですね。
ARS NOVAからは、カラヤンのロシアでのライヴ録音がまだ数タイトル発売されるようです。
今後のリリースにも期待しましょう。
(2002.5.12記)